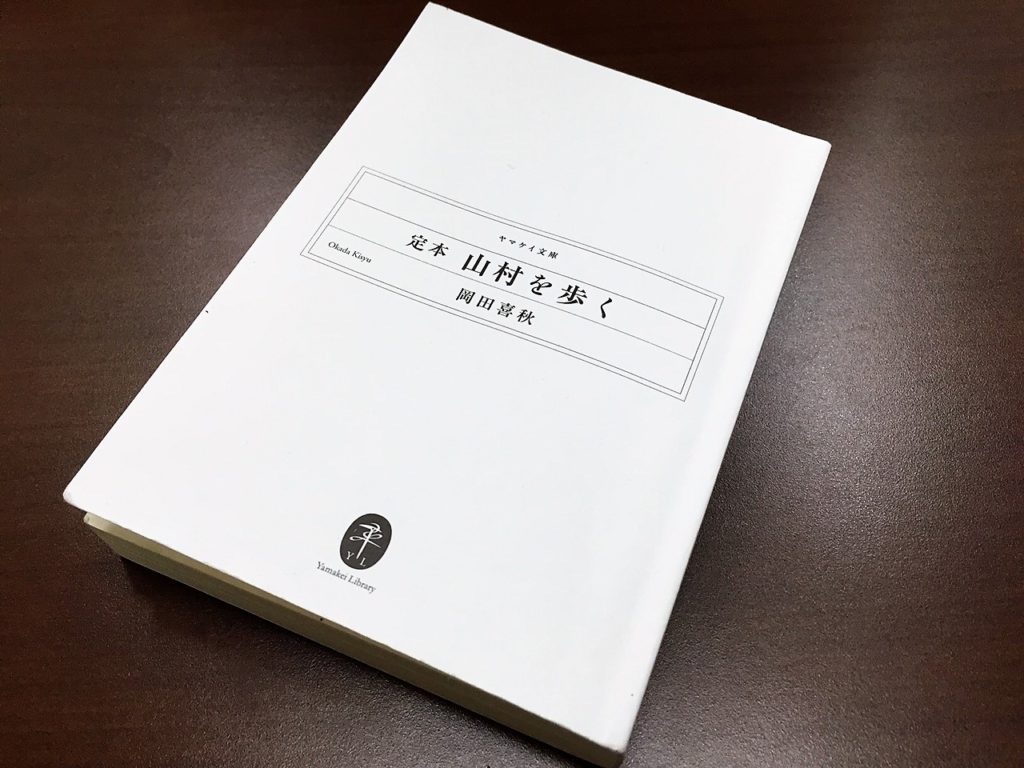hisashinakai
🖋 定本「山村を歩く」を読み思ったこと
年の始めの一冊は、その年をよりいい気分でスタートさせてくれるものに限る……
と思いつつ、昨年末に用意しておいた一冊である。
著者は知る人ぞ知る雑誌『旅』の元編集長・岡田喜秋氏だ。
“1970年代の日本の山村を探訪した紀行”とあるように、ヤマケイ文庫による渾身の復刊であり、ボクが最も弱い“定本”の二文字が付く。
さらに、そのあまりの“見事さ”に、旅の原点をズシリと再考、そして再認識させてくれた一冊となった。
もともとよく出かけてきたが、山村(里)を歩くというのは、単なる自然に浸るという楽しみだけではない。
ずっと前から、一帯に漂うさまざまな物語、簡単には言えないが、自然と生活の匂いを感じとるようなことだと思うようになった。
歴史の大きな流れとつながったりする山村もあるが、ほとんどが普通に日常の時間を積み上げ、その存在を継承してきた。
しかし、山村に限らず、そんな普通の時間しか持たない場所は少しずつ継承されなくなりつつある。
小さな文化は無意識のうちに伝承されてきたが、それらは大切にされなくなっている。
安直な話をしたくないが、言葉では、心の内では諦めきれない存在だと認めながらもだ……
この本の中で、著者はほとんどを歩いている。
だからこそこのタイトルなのだが、峠を越え、自分を追い越していくクルマもいない道を歩いて目的の場所をめざしている。
地名への思いやその道をかつて歩いたであろう人たちへの思いなど、そして、「ふるさと」を意識させる風景や人、人の言葉や出来事、その他諸々のモノゴトを混在させながら旅の余韻を残していく。
そして、この紀行文集は、たぶんどこかで見たことのあるような山村に、新しい空気感を創造し、その中へと読者を導いてくれるのである。
そして、それが“見事”なのだ。
そして、それが今の時代に生きる者として切ないのだ。
年の始めの一冊。
完読直前だが、読みながら、春になったら残雪がまぶしい明るい山村を歩きに行こうかなと思っている………